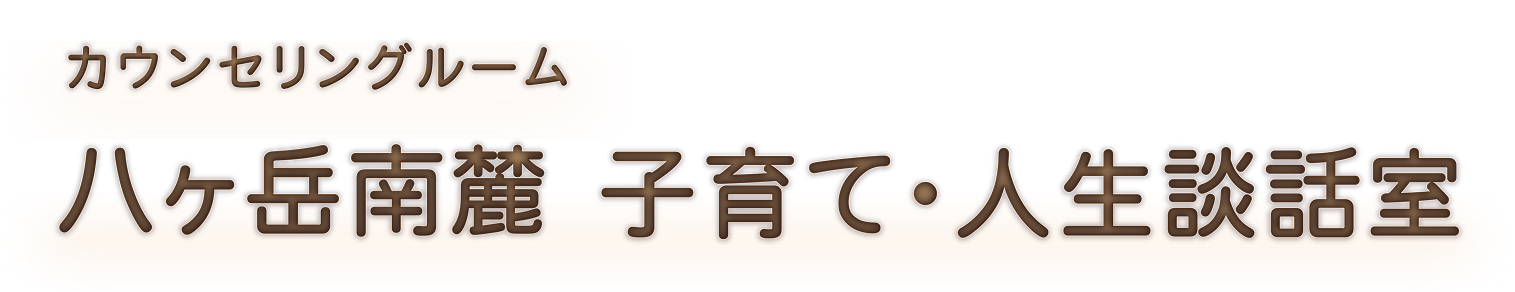プロフィール

八ヶ岳南麓「子育て・人生談話室」
代表 / 小池 一彦
- 養護学校、小学校・情緒障害児学級など障害児教育を中心とした17年間の教員生活を辞し、2002年春、山梨英和大学 人間文化学部に3学年より社会人編入学、心理カウンセリング分野を専攻
2004年春、首席で卒業 - 卒業後、(社)日本心理学会が認証する「認定心理士」の資格を取得、当談話室を開設
- 元・長野県スクールカウンセラー(2004年~21年間)
- 元・私立さくら国際高等学校・高校カウンセラー(2008年~17年間)
- 前・長野県総合教育センター夜間電話相談員
私は現在65歳。妻と大学を卒業し、35歳になる娘を筆頭に29歳の末息子までの4人の子どもと母との7人家族です。
実はこんな家族を持ちながらこの年にして、21年前に自分の生き方を公務員である小学校教員から自営の「子育て・人生談話室」へと針路変更した「無謀者」でもあります。
2002年の春から2年間、大学の心理カウンセラー養成課程で心理学の基礎を3学年からの編入学で学び直し卒業しました。
その後、取得単位の申請で得られる「認定心理士」という認証資格を元にカウンセリングルームを開設し、今年22年目を迎えるに至りました。
それと並行して長野県のスクールカウンセラーにも採用され、長野県のスクールカウンセラーとして長野県の公立高校や公立小・中学校での実践も21年間、さらに縁あって私立・さくら国際高等学校(長野県・上田市)での実践も17年間、それぞれ長きに渡り勤めさせていただき、生徒さんや保護者の方々の支援を中心に先生方へのコンサルティング保護者の方々の支援を中心に経験を重ね、取り組んで参りました。
養護学校生7年を含む15年間

私は17年間の教員生活のうち養護学校生活7年を含む15年間、障がい児教育に携わってきました。
その中で感じさせられたことは、障がいを持った子どもたちの純真な心に映し出される私自身の心の在り様です。
子どもに寄り添うことができ生き生きと活動している自分や、疲労やストレスが溜まり充分に寄り添うことができずにイライラしている自分など、子どもさん一人ひとりがそうした私の心の在り様を純粋に反映し、この上なく輝かしい笑顔を向けてくれたり、逆に怯えたような表情で落ち着きを欠いた状態を見せてくれたりしながらその時々の私の様子を的確に知らせてくれていたのです。このような生活の中で徐々に強めていったのは「健常者と言われ、かつ大人である私の心よりも、障がい児と呼ばれる子どもたちの心の方がより純粋で人間らしくあるために大切な暖かさや自然に人を信じようとする清らかさを深く、揺ぎなく備えているのではないか?」という漠然とした疑問でした。
意識的に社会の一員として生活していくこと以前に、その子がその子としてそこに在ることの大切さ、その子が社会に合わせるのではなくて、社会がその子に寄り添って柔軟に変化していくことの大切さを、折りある毎に伝えられながら過ごしていました。
「ありのままの自分で居る」ことの大切さ
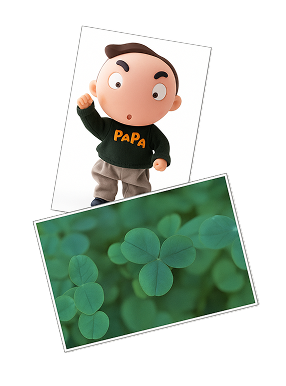
やがて私は37歳を迎え、自分が心身症であるということを受け入れ、心の問題に向き合わねばならなくなりました。
心理学の世界で「思春期の危機」と並び、近年より多く語られるようになった「中年期の危機」を乗り越えるための機会が私に巡ってきたと言えます。
具体的には、カウンセリングやグループワークにおける「自己への気づき」の機会です。そこで気づかされるのは善いところばかりではありません。多くの悪いところ醜いところも含みます。
それら全てが、掛け替えのない自分の一部なのだということに気づかされ、徐々に自己受容できるようになっていきました。自分の醜い部分はそれを嫌って無意識の方へ追いやってしまうこともできるのですがそうしている以上、真の安らぎを伴った幸福感には辿り着けません。
むしろ最初は受け入れることを拒否したい気持ちが強くても徐々に自分の一部として認められると、その方がより安心できるという真実が体験的に理解できるようになっていきます。
このような中で私は心のゆとりや自信を強め「ありのままの自分で居る」ことの大切さを実感できるようになってきたのです。
「子どもたちの真直ぐな心に、私たちは守られ、今を生きている」

それと並行して私はユング深層心理学や、親鸞聖人の浄土真宗を中心とする仏教の教えに学ぶことを通して、これまでの人生や心の変遷過程を心理学的に裏づけることができたように思います。
殊にユング心理学を学ぶ中で、子どもの心と私たち大人の心はどちらが優れていてどちらが劣っているというのでもなく、またどちらが成熟していてどちらが未熟であるというのでもなく
「その時、その瞬間、唯、共に違ってそこに在る」という重要な点が知れてきました。
そして共に違うからこそ互いが互いの不足部分を照らし合い、補い合い、死を迎えるその瞬間までそれぞれに成長し合っていくことができるのだという自覚が深まってきたのです。
言い換えるならば、大半の人間は成人し大人になっていく過程で誰しも心の奥に持っている「思いやりの心や慈しみの心」をいつしか忘れ、「物質的に恵まれ社会的に認められること、それこそが幸せなのだ」という強い錯覚を持ってしまいます。
また、周囲の期待に応えられている間は自分を信頼することができても、期待に応えられなくなった瞬間から大きな不安を感じ、信じるよりも疑うことを優先させてしまうことがよくあります。
同様に、周囲の人に対しても自分の期待に応えてくれている間は信頼することができても、期待を裏切られた瞬間から信頼できなくなることもよくあるように思います。
一方、子どもたちは大人のように固持しようとする価値観をまだ確立していないため、逆に心の奥深くに持っている思いやりや慈しみの心と直に触れ合うことができているのです。
実は私たち大人が「子どもの面倒を見てやっている」ようでありながら、逆に子どもたちの柔軟な心の方が思いやりや慈しみの心と呼応しながら、欲望にまみれて傲慢になりがちな私たち大人の在り様を広く暖かく包み込み支えてくれているのだと、私は深く気付かされてきたのです。
どんなに辛く当たろうとも「お父ちゃん」「お母ちゃん」と呼びながら、最後まで親を信じようとする子どもたちの真直ぐな心に私たちは常に守られ、今を生かされているのだと思います。
私は心のことを学ぶ中で、こうした確信を強めてきました。気づいてみるとこの確信は、私が障がい児教育に携わっていた頃に心のどこかで感じ始めていた「子どもたちの方が、より人間らしい心を持っているのではないか?」という大きな疑問の答えだったのです。
子どもの様々な問題行動に対して〇〇症、〇〇障がいと種分けをして理解していくことも意味があるのかもしれませんが、私はそのことにあまり大きな意味を感じません。
私たち大人が一人ひとり確かに違うのと同様、疾患や障がいの有無にかかわりなく、子ども一人ひとりがその子としてそこに居る。唯、それだけなのです。それだけで好いのです。
そうしたことの意味をより深くより柔軟に気づき直していくことの大切さを今、実感しています。